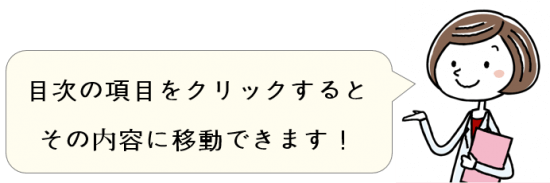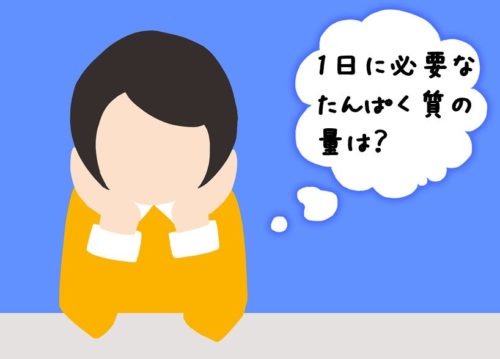きちんと食べているのに、食欲が止まらないってことはないですか?そんな人は、もしかしたら身体のたんぱく質が不足しているのかも。
「人は、必要な量のたんぱく質を摂るまではカロリーを摂り続けてしまう」というプロテインレバレッジという仮説があります。これを逆手に取ると食欲を抑制できそうです。
今回はこの仮説とたんぱく質の賢い摂り方をご紹介します。
CONTENTS
1.食欲に関係する「プロテインレバレッジ仮説」とは?
「食べてもお腹が空くのはたんぱく質不足!プロテインレバレッジ仮説」をお届けします。
美肌のために食べ物が大切ですが、健康を維持する上でも大切ですね。
さて、エイジングケア世代の女性の中にもこんな風に思ったことがある方が多いのでは?
「食べても、食べても、お腹が空いてしまう」
「やめようと思っているのに、お菓子を食べる手が止まらない」
「ダイエット中で、空腹感がおさまらない」
実は、食欲のコントロールに、「たんぱく質」が関係しているのをご存じですか?
2005年にオックスフォード大学教授のSteve J Simpson博士が『プロテインレバレッジ仮説』を発表しました。
これは、「人は必要な量のたんぱく質が摂取できるまで、摂取カロリーを増やし続けてたんぱく質を摂ろうとする」、つまり、食欲とたんぱく質の摂取量が逆相関関係になっているという、興味深い仮説です。
1日3回きちんと食べているのにお腹が空いて仕方ない人や、年末年始、いつもよりつい食べ過ぎてしまって太ったからだを元に戻すのが大変、という経験をされた方もいるのではないでしょうか。
このプロテインレバレッジ仮説を利用すれば、食欲をコントロールすることも可能です。
今回は、このプロテインレバレッジ仮説に関する研究結果とともに、たんぱく質を取り入れる食事の仕方をご紹介します。
2.1日どれくらいのたんぱく質量で、食欲を抑えることができるか?
食欲は、人間が生きていく上で重要な生理的な三大欲求のうちの一つです。食べることでエネルギーを生み出し、からだを維持するのに必要な栄養素を血中から細胞に送り込んでいます。
ですが、現代は食べ物も豊富で、ジャンクフードやスナック菓子などがあふれています。自分では、バランスよく食べているつもりでも、脂質や糖質を摂り過ぎる傾向にあるのかもしれません。
糖質の多い食事をしていると、食後すぐに空腹を感じます。なぜなら、糖質が多い食事は、血糖値を急上昇させたあと急降下させるからです。そのため、糖質をエネルギー源としている脳が、エネルギーが不足していると判断して「もっと食べて!」と指令を出すわけです。
ダイエットしている時は糖質や脂質を極力減らすようにしますから、常に空腹感にまとわりつかれるんですね。
また、現代の日本人はインスタント食品などの普及で、1日のたんぱく質の摂取量が十分ではない人が多いといわれています。
「たんぱく質の摂取量が不足していると、必要量に達するまで、食欲はどんどん増していく」という可能性のあることが、プロテインレバレッジ仮説のいくつかの研究からわかっています。
1)プロテインレバレッジ仮説の代表的な研究3つ
(1)シドニー大学のGosbyらの発表(2011年)
被験者22名にたんぱく質の比率を増やした食事をしてもらったところ食欲が減少したという研究。
(2)マーストリヒト大学のMartensらの発表(2013年)
79名の男女にたんぱく質の比率を変えた食事をしてもらった結果、高たんぱく食の方が自然に総摂取カロリーが減少したという研究。
(3)シドニー大学のGosbyらの発表(2013年)
過去に発表された38の報告を調査し、たんぱく質の摂取量が増加するほど総摂取カロリーは減少する傾向がみられたことを報告。
2)食欲を抑えるために、1日にどれくらいたんぱく質を摂ればよいのか?
結論から言いますと、「最低でも、総摂取カロリーの15%をたんぱく質として摂ることで、食欲は抑えられる」ようです。
この根拠は、上記の論文(2)の報告の結果です。この研究では、食事の条件は以下の通りで実験が行われました。
- カロリー制限はなく、食欲のままに食べる
- 試験最初の4日間は総摂取カロリーの10%をたんぱく質にする
- 続く4日間は総摂取カロリーの15%をたんぱく質とした
- 最後の4日間は総摂取カロリーの25%をたんぱく質とした
そうしたところ、得られた結果が以下のとおりでした。
- たんぱく質の量が10%のときが、最も総摂取カロリーが増加
- たんぱく質の量を15%から25%に増やしても、空腹感に変化はみられなかった
- 摂取量の10%をたんぱく質という食事を続けていると、経時的に総摂取カロリーが増加
つまり、1日の総摂取カロリーのうちたんぱく質の量は、最低ラインとして15%は摂れば食欲は抑えられるということです。
3.自分に必要な1日のたんぱく質量を知ろう
1)1日に摂取するたんぱく質の必要量はどれくらい?(厚生労働省の推奨量)
①厚生労働省が定める1日の推奨量は、ゆで卵なら7個以上
厚生労働省の「日本人の食事摂取基準 (2020年版)」では、1日のたんぱく質の摂取量として、成人男性が60g、成人女性が50gとして推奨しています。この量を摂っていると、たんぱく質不足を回避できるというレベルのものです。
女性の1日推奨量50gを食物から摂るとなると、例えば、以下の食品だとこんな風になります。
- 納豆(30g)10パック
- 絹ごし豆腐(300g)3.4丁
- サラダチキン(115g)2つ
- ヨーグルト(100g)11.6個
- ゆで卵(Mサイズ、50g)7.7個
食品からだけでたんぱく質を摂取するとなると、かなり大変そうですね。
②50代以上では、たんぱく質の摂取目標量が引き上げられる
P(Protein たんぱく質)
F(Fat 脂質)
C(Carbo 糖質)
を略してPFC。
この3つの比率を「PFCバランス」と言います。
諸説ありますが、PFCバランスの黄金比率というのがあります。
黄金比=(P)20%:(F)40%:(C)40%と言われています。
今回、5年ぶりに改定された、厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」ですが、この中で、50歳以上のたんぱく質の摂取目標量のPFCバランスの下限が引き上げられました。
これまでは世代に関係なく、たんぱく質の摂取目標量としては、PFCバランスの13~20%とされていました。
しかし、2020年版では50~64歳:14~20%、65歳以上:15~20%と設定されました。
これは現代人のたんぱく質不足を解消しようとする意図があります。
なぜなら、たんぱく質不足が、いま問題となっているフレイル(体の働きが弱くなってくる状態)に影響すると考えられているからです。
フレイルは高齢社会を迎える中では大きな問題となっています。
だから、フレイルになる人々を減らすことが社会的にも大切なことなのです。
また、健康な状態と要介護へと移る中間の段階と言われるフレイルは、加齢に伴う筋力低下などだけでなく、口腔を介して全身へと影響するオーラルフレイルもあります。
詳しくは、「老化に影響大の「オーラルフレイル」。危険性がある人は5割超え!」をお読みください。
<参考>
日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定検討会報告書.各論1-2 たんぱく質. 厚生労働省.
2)1日の総カロリー摂取量を計算する方法「TDEE」と「PFCバランス」の計算方法
そもそも、1日に必要なカロリー摂取量は人それぞれです。年齢や体型による基礎代謝量、日常生活の活動量によっても変わってきます。
だから、厚生労働省の推奨量も念頭に置きつつ、自分自身に必要なたんぱく質の最低量も把握しておくことをオススメします。
その方法として、「TDEE」を計算してみましょう。
TDEEとは、Total Daily Energy Expenditureの略で、1日の総消費カロリーのことです(基礎代謝量に一日の活動カロリーを足したもの)。
TDEEの計算は、ウェブで「TDEE」と入力すれば計算できるサイトがいくつもヒットしてきます。また、スマホのアプリもいくつもありますので、ご自分に合ったものをご利用ください。
参考として、いくつかあるウェブサイトの中から1つご紹介します。
▶Ke!san 生活や実務に役立つ計算サイト(カシオ計算機株式会社)
そして、PFCバランスを計算しましょう。できればPFCバランスも計算できるツールを利用するのが便利です。
もし、TDEEをもとに計算するなら、以下を一つの目安としてください。
たんぱく質(P):体重1kgあたり2gの摂取を目安
脂質(F):TDEEの25~30%を目安
炭水化物(C):TDEEからたんぱく質と脂質を引いた数値
4.空腹感を抑えるための、賢いたんぱく質の摂り方
たんぱく質が不足すると、イライラする、集中力低下、ストレスによる肌荒れ、シワやたるみ、顔のくすみ、むくみ、枝毛や切れ毛、髪ツヤ低下、貧血、筋力の低下、爪が割れやすくなったり、縦筋が入る、からだが疲れやすくなるなどの原因となります。
こんな症状が見られたら、もしかしたら、たんぱく質が不足しているかもしれません。
だから、健康のためにもたんぱく質を適切な量を摂ることが大切です。
1)食物からのたんぱく質の摂り方
さて、たんぱく質には植物性と動物性があります。
植物性たんぱく質は、大豆たんぱく、小麦たんぱくに分類されます。大豆たんぱくは、女性ホルモンの1つであるエストロゲンと似た働きがある大豆イソフラボンや、抗酸化作用があるポリフェノールが豊富です。女性にとっては、健康や美肌維持などカラダの内側からアンチエイジングとエイジングケアができる栄養素ですね。
一方、動物性たんぱく質は肉類、魚介類、卵などで、必須アミノ酸を含んでいます。
例えば、1日のどれか1食を、お米やパンではなくてゆで卵や肉・魚にする、プロテインを飲んでから食事を摂るなどしてはいかがでしょうか。
植物性・動物性の2種類のたんぱく質をバランスよく一緒に摂ることで、相乗効果が期待できます。
2)サプリメントでたんぱく質を賢く摂る方法
また、先ほどご紹介しましたが、1日に必要なたんぱく質を食品だけから摂るのが難しいときは、不足分はサプリメントをとりいれて、賢くたんぱく質を摂るのがオススメです。
例えば、プロテインの利用は筋肉を作るのに効果が高いとされています。でも、プロテインの取り過ぎや運動をしていないとカロリー過多になって、太る可能性があります。また、肝臓や腎臓に負担をかける可能性があるので、肝臓や腎臓に疾患のある人は主治医と相談してください。
その他に、コラーゲンサプリメントで摂るのもオススメです。
コラーゲンの正体はたんぱく質(アミノ酸)で、人のからだ全体の6%、真皮の70%以上をコラーゲンが占めています。
エイジングケア世代の女性では、年齢とともにコラーゲンが低下していきます。だからコラーゲンでたんぱく質を補うことで、空腹感だけでなく、真皮にある線維芽細胞をイキイキした状態に維持して、皮膚の健康、お肌のハリやツヤ、髪、爪の健康もキープできます。
<サプリメントなどに使われるコラーゲンについて深く知りたい方への参考記事>
*マリンコラーゲンとフィッシュコラーゲンに大きな違い!真実は?
*プルプル美肌になる!コラーゲンサプリメントの種類と選び方のコツ
*コラーゲンを毎日食べて、紫外線による光老化や肌老化を予防しよう!
*コラーゲンの敵!紫外線による光老化から肌を守るコラーゲンペプチド
<からだの健康や美肌を維持するための食事方法の参考記事>
<PR>
★天然マリンコラーゲンの純度100%の低分子純粋コラーゲンなら★
添加物・着色料・香料は一切含まれていません。
5.編集後記
「食べてもお腹が空くのはたんぱく質不足!プロテインレバレッジ仮説」をお届けしました。
1カ月前くらいから、スマホのアプリを利用して食べたものを記録しています。TDEEに基づいてPFCバランスのチャートが表示されるのですが、たんぱく質の摂取が満たっていなくて、脂質がかなりオーバーしているということがわかりました。それを見て、毎日食べるものを気をつけるようにしているのですが…。
ほんのちょっとした油断、例えば、疲れたからチョコレート1粒だけでも食べると、脂質・糖質に加算されるので、PFCバランスを見ると、自分の甘さにがっかりします。少しずつでも改善していきたいと思っています。
この「食べてもお腹が空くのはたんぱく質不足!プロテインレバレッジ仮説」が、ナールスエイジングケアアカデミーの読者のみなさまのお役に立てれば幸いです。
著者・編集者・校正者情報
医学出版社、医学系広告代理店にて編集・ライターとして、医師向け、患者向けの情報提供資材や書籍等の記事の編集・執筆や、国内・海外医学会取材・記事執筆を行う。
(編集・校正:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)
京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。
医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。
一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト
著作(共著)
当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。
そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報ご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。
ぜひご登録をお待ちしております。
▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから
nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」
SNS Share
\ この記事をシェアする /