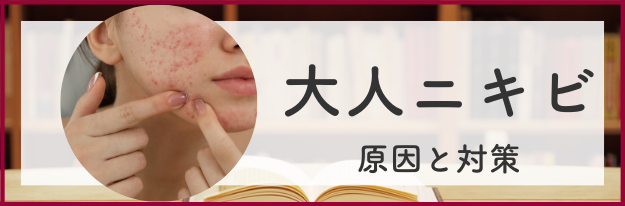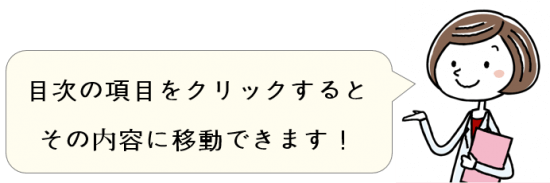春は寒暖差の大きい日が続くことで、心の浮き沈みが激しくなりがち。
しかし季節的なものだけでなく、春は年度末・年度はじめということから、変化も大きい時期でもあります。
そんなときは、知らず知らずのうちにストレスをためてしまっているかもしれません。
過剰なストレスは、メンタルだけでなく肌にもダメージを与えるため、肌荒れなどの原因になることも。
この記事では、ビューティーアロマ認定講師の北口慈子さんに、香りのメカニズムからメンタルケア方法、スキンケア方法をご紹介いただきます。
<2章から4章までの執筆>

北口慈子
元美容部員の美容ライター。
美容部員時代、化粧品をなんのために使っているのかわからず、いわれるがままに化粧品を購入し、結局使っていない人が多いことに愕然。流行りの化粧品やおすすめされたものを使っても理想の肌に近づかない…そんなお悩みを抱えている方のお手伝いがしたい!と考えるように。「今の自分が本当に必要としている化粧品を、自分で選べるようになってほしい」という想いを軸に活動中です。
スキンケアだけでなく、メンタルも美容に深く関わっていることから、日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラーとして「心の美容」もサポートさせていただいています。
◆ 専門・得意分野
美容、メンタルケア
◆ 保有資格
◇日本化粧品検定1級◇コスメコンシェルジュ◇コスメライター◇ビューテーアロマ認定講師◇ナチュラルビューティースタイリスト◇認定心理士◇日本メンタルヘルス協会公認心理カウンセラー
化粧品の魅力TELLER
*大人ニキビの原因と対策の全てがわかる!|エイジングケア化粧品のナールス
CONTENTS
1.春のストレスによる肌悩みを香りで対策したいあなたへ
「春の変化によるストレスと肌悩みは香りで癒されて対策を」をお届けします。
春の寒暖差が大きい日が続くと、「肌荒れが気になるな…」と思うことはありませんか?
気温だけでなく、春といえば「変化の季節」。
年度末・年度初めということで、人間関係や職場環境など、多くの変化を感じる時期でもあります。
だから、もしかすると春の肌荒れなどの肌悩みは、寒暖差だけでなくストレスが関係しているかもしれません。
なぜなら、脳と肌は自律神経によってお互いに影響を受けるからです。
人は受精卵から胎児になる際、内胚葉・中胚葉・外胚葉の3つに細胞が分かれます。
実は、皮膚の表皮と脳神経は、外胚葉からできていくのです。
このように、皮膚と脳は、同じ細胞がルーツなので、密接に繋がっているのです。
だから、脳神経、つまり心が良くないストレスを感じると、肌にも影響を与えるのです。
逆に、楽しい、嬉しいという感情が生まれると肌にも良い影響を与えます。
では、どうすれば良い刺激を脳や心に与えて肌を健やかにできるのでしょうか?
そのためには、香りを味方につけるのがおすすめ。
香りは、フランスをはじめ諸外国では「アロマテラピー」という自然療法として用いられていますが、日本ではアロマは「香りを楽しむもの」というイメージではないでしょうか?
しかし、香りの仕組みを知れば、肌とメンタルのバランスを保つサポートをしてくれることがわかります。
つまり、香りによって肌荒れなどの肌悩みの予防や改善が期待できるのです。
そこで、この記事では、ビューティーアロマ認定講師である北口慈子さんに、ストレスによる自律神経の乱れと肌悩みとの関係性とともに、香りの心身への効用について解説していただきます。
また、どのような場面でどんな香りを使えば、心身や肌に良い影響を与えるのか、さらに、使い方の注意もご紹介します。
<参考記事>
*春の肌トラブルや肌悩みはスキンケア&エイジングケアで解消!
2.「アロマ」の香りの歴史と今
香りといえばすぐ思いつくのがアロマ。
この記事では、アロマの香りを中心に肌悩みへの使い方をご紹介します。
そこで、この章ではアロマの歴史や医療との関係、日本の現状について触れてみます。
医療分野で使用するアロマのことを「メディカルアロマ」と呼びます。
世界ではアロマを医療分野に取り入れている国はたくさんありますが、日本ではまだまだアロマは「香りを楽しむもの」という認識が強いのではないでしょうか?
まずはアロマの歴史を紐解き、どのように利用されてきたのかをお伝えしながら、メディカルアロマの発祥の地や、そもそもメディカルアロマとは何なのかについてご紹介します。
1)アロマの歴史は古い?
アロマ、つまり香りは紀元前3000年のエジプトにおいて、美容と健康をサポートするものとして儀式などに使われていたもので、昔から身近な存在だったといわれています。
とくにミイラ作りには、フランキンセンスやミルラなどの精油が用いられていたそうです。
ミイラが腐らずに現代まで形を残せていたのも、これらの精油のおかげだという説もあります。
西洋では、さまざまなハーブが体調管理をするアイテムとして修道院などで使われ、また民間療法に用いられていたそうです。
11世紀になると蒸留器が開発され、植物を蒸留してエッセンシャルオイルがつくられるように。
この時代から、ローズなどの植物から取れるオイルを医療として使用していたといわれています。
また、エッセンシャルオイルをキャリアオイルで希釈をするという方法がヨーロッパ各地で拡散したのもこの時代です。
20世紀に入って誕生したのが「アロマテラピー」という言葉。
これはフランスの科学者である、ルネ・モーリス・ガットフォセが、「アロマ=芳香」と「テラピー=療法」の2つの言葉を組み合わせてつくった造語です。
日本では、西洋医学が普及するようになった江戸時代あたりに、精油を用いた医療が伝えられたといわれています。
日本でも、古くから精油が薬として用いられていた歴史があるのです。
その後、第二次世界大戦を経て、現代のメディカルアロマの形態ができたといわれています。
というのも、第二次世界大戦時には医療物資が不足し、フランスではエッセンシャルオイルを負傷した兵士たちに使用していたという歴史があるそうです。
その使い方はさまざまで、たとえばラベンダーであれば、不眠や頭痛、メンタルケアに用いたことから、メディカルアロマが確立されたようです。
ほかにも、17世紀に南フランスで大流行をしていた感染症のペスト(=黒死病)にまつわるアロマの歴史もあります。
それは、ある泥棒4人組がペストに感染して亡くなった人たちから金品を盗んでいたにも関わらず、まったくペストに感染しなかったというエピソード。
彼らは捕まってしまうのですが、死刑を免除する代わりにペストに感染しなかった秘密を教えることになったのです。
そこで登場したのが、ローズマリー・タイム・セージ・ラベンダー・ミントなどのハーブをお酢に漬け込んだハーブビネガー。
彼らは、殺菌効果の高いハーブビネガーをつくり、全身に塗っていたことから感染症にならなかったそうです。
このように、植物から取れたオイルを希釈したり、漬け込んだりしたものを負傷した人に用いたり、消毒として用いたりする方法が、現代のアロマテラピーやメディカルアロマに通じているのです。
2)メディカルアロマとは?
「アロマ」と聞くと「香りを楽しむもの」という印象をお持ちの方は多いのでははいでしょうか?
日本では、とくに好きな香りを焚いて、気分をリフレッシュさせる「芳香」を目的として用いることが多いでしょう。
しかしヨーロッパ、とくにフランスでは医療として認められている治療方法の一つという立ち位置です。
もちろん、保険も適用されます。
植物療法をイメージしていただけるとわかりやすいかもしれません。
アロマを医療で使う方法としては、飲む・塗るという形が取られ、医療品としての扱いになっています。
日本ではあまりなじみがないかもしれませんが、漢方や生薬、薬草をイメージすると理解しやすいでしょう。
アロマテラピーは、100%植物から抽出された「精油」を利用するのが特徴で、リラックス効果、体調不良の改善、心身の強壮など、精油の種類によってさまざまな効果が得られるといわれています。
3)メディカルアロマの発祥は?
メディカルアロマテラピーはフランスで発祥したといわれています。
歴史のところでもお伝えしたように、ヨーロッパでは昔からハーブが身近な存在であり、民間療法に使われていただけでなく、戦時中の医療でも役立てられていました。
そのフランスはもちろん、ベルギーなどの諸外国、とくにヨーロッパでは、現代でも医師がアロマを治療として使用しているのです。
それが「メディカルアロマテラピー」です。
日本では、医師がメディカルアロマを処方することはほとんどなく、処方されたとしてもそれはあくまで「補完的なもの」として。
日本では、まだしばらくは、香りを「楽しむもの」として使っていくことになりそうです。
とはいっても、私たちが上手にアロマ、香りを使えば、健康や美肌にために役立ちます。
次の章からは、香りをストレス解消や肌荒れなどの肌悩みに上手に活かす方法をご紹介します。
<参考記事>
3.香りがストレスによる肌荒れに良い理由は?
寒暖差の大きい日が続いたり、環境の変化が大きい日があったりする春は、疲れやストレスがたまりがち…。
そんなときこそ、香りを有効活用するのがおすすめ。
なぜ香りが良いのか、まずは香りを感じるメカニズムからご紹介し、どのような作用をするのかについてもお伝えします。
1)香りを感じるメカニズムとは?
五感(視覚・聴覚・触覚・味覚・嗅覚)の中で、嗅覚だけは理性をつかさどっている視床・大脳新皮質を通らず、本能行動や感情、記憶を司る大脳辺縁系の偏桃体や海馬に直接伝わります。
その速さはなんと約0.2秒といわれています。
香りを感じるメカニズムを詳しく説明していきます。
まず、香りは嗅上皮という鼻腔最上部の粘膜に溶け込んで感知されます。
嗅上皮にある嗅細胞の先端部分には嗅毛と呼ばれる嗅覚受容体があって、香りの分子情報が結合されます。
すると、嗅細胞が電気信号を大脳辺縁系へと発信します。
そこで情報処理がされることで、私たちははじめて「ニオイ」として認識するのです。
さらに、この電気信号は、自律神経・内分泌機能・免疫機能の中枢といわれている視床下部に届きます。
これが香りを感じるメカニズムです。
このように、人間の生理的な活動をコントロールする自律神経系に影響を与えることから、香りは心身のバランスを整えるのに有効です。
2)香りがどのように心・身体・肌に作用するのか
香りは理性の脳を通らない分、本能的なところからはたらきかけてくれます。
それぞれ、どのようなはたらきかけをしてくれるのか、お伝えします。
①心への作用
好きな香りを嗅ぐと、リラックスしたり、心が落ち着いたりしませんか?
それは香りに刺激を受けた脳が神経伝達物質を分泌しているから。
たとえば、感情を落ち着かせてくれたり、安定させてくれたりするセロトニン、やる気や興奮をもたらすアドレナリンなどはどちらも脳内伝達物質です。
香りを感じる部分と感情をつかさどる脳の部分が近いことも、心へはたらきかける要因の一つといえるでしょう。
②体への作用
エッセンシャルオイルなどの植物由来の香りには、その種類ごとに抗菌・消化促進・免疫強化など、体への作用もあるといわれています。
鼻だけでなく、口・腸・皮膚など、体内に取り入れる方法はいくつかありますが、それが毛細血管に乗って全身を巡ることで、さまざまな器官にはたらきかけてくれるのです。
③皮膚への作用
もちろん美容にも活かされるのが香り。
ラクトンという香り成分は、紫外線による炎症を抑えることが知られています。また、香りが皮脂のバランスを整えたり、肌を引き締めたりなど、肌の調子を整え、美容のための作用も期待できます。
4.香りで肌悩みのスキンケアを!おすすめのエッセンシャルオイル
化粧品でも幅広く配合されていることの多いエッセンシャルオイル。
最近では、手作りコスメを自分で楽しむ方も増えてきました。
そこに香りを楽しめるエッセンシャルオイルを1~2滴ほど垂らすだけで、肌悩みに合わせたオリジナルアイテムが完成します。
ここでは、聞きなじみのある香りから少し変わった香りまで、スキンケアアイテムに用いられることの多い香りをご紹介します。
1)ラベンダー
ラベンダーは、誰もが聞いたことのある香りの一つではないでしょうか。
よく知られているのはリラックス効果。
ほかにも抗菌作用や安眠効果もあるということから、介護施設でも使われています。
これらの効果を発揮させているのが酢酸リラリル。
自律神経のうち、交感神経の緊張をやわらげ、副交感神経を活発にしてくれます。
そのため、鎮静作用・鎮痛作用・血圧降下などの効果も期待されています。
2)フランキンセンス
「アロマの王様」とも呼ばれているフランキンセンスの香りは、神仏への捧げものとしても使われていました。
樹脂から採れるフランキンセンスのオイルは、「若返りのオイル」の異名を持ち、乾燥肌・肌荒れなどのスキンケアにも効果があるといわれ、エイジングケアに最適。
また、フランキンセンスは「再生力」にも注目されており、一部の国では癌治療に使われてることもあるそうです。
3)ローズマリー
料理にも使われることのあるローズマリーの葉は、フレッシュでハーバルな香りが特徴。
収れん作用や抗酸化作用に優れ、エイジングケアだけでなく、オイリーヘアやフケを防ぐのに使うのも良いでしょう。
無気力感や集中力の低下、眠気を感じたときにもおすすめ。
春の寒暖差疲れが出ている時期にピッタリの香りです。
4)ペパーミント
鼻通りが良くなるような爽やかさが特徴のペパーミントの香り。
鎮痛・消炎作用が期待され、アレルギー性の湿疹やかゆみ、日焼けなどの炎症をやわらげてくれる作用があります。
さらに、抗菌・抗ウイルスなどの効果も。
清涼感のある香りはスキンケア後にすっきり感をもたらし、ペパーミント精油に含まれるメントールにより、体感温度を下げたり、鼻詰まりを緩和してくれたりします。
5)ティーツリー
「メラルーカ」とも呼ばれているティーツリーは、抗菌・抗ウイルスにすぐれた作用をもつといわれており、大人ニキビや吹き出物がでたときの強い味方。
鎮痛作用もあり、日焼けによるヒリヒリとした痛みをクールダウンしてくれたり、かゆみをやわらげたりもしてくれます。
木のスッキリとしたオイルはスキンケアだけでなく、掃除や洗濯、消臭など生活面に使える万能な精油です。
6)アーボビデ
「命の木」として知られるアーボビデの木から抽出されるオイルは、温かみのある大地の香りが特徴。
ヒノキチオールやツヤ酸など、トロポロン類が多く含まれ、清々しく快適な空間を演出します。
季節や環境の変化が著しい春に重宝しそうな香りです。
環境の変化からくる疲労や不安、緊張にも良いと期待されています。
7)コパイバ
成長すると約30メートルもの巨木になるコパイバの木。
その幹から抽出されるオイルは、ほのかな甘さが香るしっとりとしたウッディな香りが特徴です。
オイルにβカリオフィレンを含んでおり、不安な気持ちを緩和・心を落ち着かせてくれます。
明るい気持ちにしてくれるだけでなく、鎮痛作用・消炎・収れん作用に優れているといわれています。
8)シダーウッド
ウッディな温かみのある香りが特徴のシダーウッドは、不安感や感情的になった心を落ち着かせてくれます。
リラックスタイムにはもちろん、リンパの流れを良くしたり、マッサージオイルとして使えば、セルライトやむくみにもアプローチしてくれるため、美容にもおすすめの香りです。
寒暖差の大きい日など、感情がゆらぎやすいときに持っておくと心強い香りとなっています。
9)オレンジ
フレッシュで甘く、爽やかな香りが特徴のオレンジは、アロマの代表的な香り。
気持ちを明るく前向きにしてくれるので、抑うつ的な気分のときに使いたい香りです。
緊張をほぐし、気持ちを落ち着かせてくれます。
ほかにも、血流の流れを促し、肌を活性化してくれるはたらきも。
ティーツリーと同じく、掃除や空気の清浄にも使える万能な香り。
なじみのある香りなので、比較的好き嫌いなく使える香りでしょう。
10)クラリセージ
「女性のためのハーブ」とも呼ばれているクラリセージは、ほのかな甘さがおだやかに香るやさしい香りが特徴です。
というのも、生理不順や更年期障害を緩和するなど、女性ホルモンと心のバランスを保つサポートをしてくれるハーブだから。
加えて、クラリセージの香りは、幸せホルモンと呼ばれているオキシトシンの分泌を促すといわれており、自律神経のバランスを整えるのにもピッタリ。
また、皮脂のバランスを整える作用も持っているため、脂性肌やニキビに悩んでいる方にもおすすめです。
<参考記事>
*女性ホルモンのバランスを整えて美肌をキープ!(飯塚美香さん)
11)ローマンカモミール
「植物のお医者さん」と呼ばれているローマンカモミールのオイルは、リンゴのような甘くフルーティな香りが特徴です。
消炎作用や抗菌作用があるといわれており、肌荒れしているときに使いたい香り。
抗アレルギー作用もあることから、花粉による目や肌のかゆみ、乾燥もやわらげてくれます。
フェイスクリーム・ヘアカラー・シャンプー・香水など、幅広いアイテムに使われるほか、入浴時のバスオイルとして使うのもおすすめです。
<参考記事>
12)ブルータンジー
キレイなブルーの精油が印象的なブルータンジーは、フルーティさのある甘い香りが特徴。
ブルータンジーオイルに含まれるカマズレンは、抗ヒスタミン・抗アレルギー作用に優れているといわれ、肌を落ち着かせてくれます。
免疫系をサポートする作用もあり、風邪や喘息にもよいといわれています。
<参考記事>
*風邪に抗生物質(抗菌薬)はNG!腸内細菌を乱して肌荒れのリスクも
13)ゼラニウム
ローズのような華やかさのなかに、爽やかなハーブ感を潜ませたグリーンフローラルな香りが特徴のゼラニウムは、自律神経やホルモン分泌のバランスを整える作用があり、女性にはおすすめの香り。
精神的なストレスの解消にも役立つとされており、環境の変化が大きな春にもおすすめ。
また、皮脂のバランスも整える働きがあると言われており、皮脂に悩んでいる方にもおすすめ。
ただ、酸性が強めのオイルにはなっているので、使用する場合は少量のみにしましょう。
14)ジャスミン
甘く、エキゾチックさもありながら、上品な香りが特徴のジャスミン。
ジャスミンのオイルは、約1トンの花からおよそ1kgしか抽出できない貴重なオイルです。
脳内麻薬と呼ばれるエンファリンや、快感ホルモンと呼ばれるドーパミンの分泌を活発化する作用があります。
緊張や不安を感じる場面で、心を落ち着かせ、ポジティブでリラックスした気分へと導いてくれます。
15)ローズ
「ローズ」もスキンケアアイテムに幅広く使われているエッセンシャルオイルの一つ。
ただ、ローズにはいくつか種類があり、それぞれのローズの香りで少しずつ異なる部分もあるので、特別に6章でピックアップします。
5.香りで肌悩み対策する際の注意~エッセンシャルオイルのリスクと取り扱い~
エッセンシャルオイルをディフューザーに数的垂らし、香りを楽しむ分にはとくに注意点はありませんが、それ以外の用途で使用する場合は注意が必要です。
とくに、肌に直接触れるような使い方をする場合に気を付けたいポイントをご紹介します。
1)エッセンシャルオイルは「化粧用油」として登録のあるものを使用する
香りをフレグランスとして楽しむ以外に使用する際は、エッセンシャルオイルの品質に気を付けて選びましょう。
日本では多くのオイルが「雑貨」として登録されています。
しかし、化粧品や入浴時に使用するなど、肌に直接触れる場合は、化粧用油として登録のあるものを選ぶのがおすすめ。
ホームページなどで、成分分析が明確に記載されており、公開されているものだと安心です。
2)柑橘系のオイルは光毒性があるため、日中の使用は避ける
柑橘系の香りにはソラレンという物質が含まれており、この物質には光毒性があります。
そのため、日中の使用は注意しましょう。
柑橘系の香りの中でも、とくにベルガモットは気を付けた方が良いでしょう。
3)使用前にパッチテストを行う
エッセンシャルオイルの中には、刺激を感じやすいものもあります。
普段のスキンケアアイテムでも刺激を感じやすい方、エッセンシャルオイルを使用した自作コスメをはじめて試す方などは、必ずパッチテストを行ってから使うようにしましょう。
パッチテストを自宅で簡単に行う方法をご紹介します。
まず、入浴時に二の腕の内側を石けんでキレイに洗い、清潔な状態にします。
お風呂上りに、チェックしたい化粧品を直径1cmほどの円形に並べるように少量ずつ塗布します。
30分ほど放置し、赤みやかゆみなどの異常がないかチェックしましょう。
異常がなければ、そのまま24時間追加で放置します。
その後、異常がなければフェイスラインに塗布してみましょう。
塗布後30分ほど放置し、赤みやかゆみなどの異常がないかチェックし、何もなければOK。
ただ、この方法は簡易的な方法になるので、しっかりとチェックしたい場合は、皮膚科で医師によるパッチテストを行ってもらうのが良いでしょう。
4)はやく使い切る
手作りコスメの良いところは無添加でつくれるところや、エッセンシャルオイルを加えてオリジナルの化粧品を試せるところです。
ただし、防腐剤を使用していないものは、長い期間放置しておくと傷んでしまいます。
そのため、化粧品を手作りした場合は、できるだけはやく使い切るように心がけましょう。
5)容器にもこだわる
エッセンシャルオイルは、空気や熱、光などの影響を受けやすいため、品質変異を起こしやすい性質を持っています。
そのため使用する際は、遮光性のある容器を選びましょう。
また、エッセンシャルオイルが使用できる専用の強化プラスチックボトルやガラス容器がおすすめです。
6.「ローズ」の香りは肌悩みや肌荒れにも良い!?3種をピックアップ
ローズはバラの種類により、香りはもちろん作用も異なります。
日本では化粧品に配合した場合、効能・効果を謳うことはできませんが、ローズの香りによる研究で明らかになったことも!
1)3種のローズの肌への効果
豊富な種類が特徴のローズ。
なんとその種類は20,000種類を超えるのだとか!
スキンケアアイテムでもローズの香りは女性に人気ですよね。
さらに、ローズはエレガントな香りを楽しめるだけでなく、研究により、香りの種類によってさまざまな効果が確認されています。
今回は、化粧品にも幅広く利用されている3種類のバラの香りをピックアップしてみました。
①ダマスクローズ
「バラの女王」とも呼ばれているダマスクローズは、高貴な香りで大人女性に人気。
とくに、ブルガリア産のものは最高級といわれています。
そんなダマスクローズには保湿とやわらかな抗菌作用が期待されていることから、エイジングケア成分として使われることも。
防腐剤の配合も少なく済むことから、化粧品に使われることの多いバラの香りです。
②センチフォリアローズ
センチフォリアローズも、バラの女王と呼ばれているダマスクローズに引けを取らないくらい甘く、豊潤な香りが特徴のバラの一種。
化粧品に配合されるときは、「センチフォリアバラ花エキス」と表示されています。
センチフォリアローズも大人女性に嬉しいエイジングケアができる成分。
そのはたらきとしては、肌のハリ・弾力を支えているヒアルロン酸を分解する酵素のはたらきを阻害すること、そしてもちろん保湿効果も。
抗菌作用や血流改善の作用も期待されているバラの香りです。
③イザヨイバラ
あまり聞かないバラの品種かもしれませんが、イザヨイバラには美容に嬉しい成分がギュッと詰まっています。
ビタミンC・タンニン・アミノ酸などだけでなく、肌のうるおいに欠かせないセラミドを増やすサポートをしてくれます。
バリア機能を正常化してくれるため、肌荒れしにくい健やかな肌へと導いてくれます。
2)バラの成分で抗うつ効果も!
これらバラに含まれる香り成分である「フェニルエタノール」は、研究によって「抗うつ効果」が明らかに!
これは、川崎医療福祉大医療技術学部の上野浩司講師らの研究グループによって発見されました。
より詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
<参考記事>
*バラの香り「フェニルエタノール」の抗うつ効果と攻撃性を抑える効果
7.春にピッタリ!ローズの香りを持ち歩くならナールス ロゼ
スキンケアアイテムだけでなく、香りを楽しめるアイテムはたくさんあります。
フレグランスはその代表格ですが、今回は先ほどご紹介したローズの香りがふんだんに使われたハンドケアアイテム、ナールス ロゼをご紹介させていただきます。
なぜ、ハンドケアアイテムをピックアップしたかというと、手は手袋をしない限り隠せない部分でありながら、スキンケアほど力をいれてケアをしている方が少ないから。
紫外線の影響や手洗い・アルコールによる手肌の乾燥など、肌トラブルが出やすい箇所です。
しかし、手のケアをしていないと、老け見えの原因となってしまいます。
そこで、今回おすすめするのがナールス ロゼ。
ナールスならではのエイジングケア成分でもあるナールスゲン*が配合されています。
さらに、美容成分としてバラの女王と呼ばれているダマスクローズ(保湿・整肌成分)を配合。
ハンドクリームではなく、「ハンド美容ジェル」と呼ばれているナールス ロゼは、美容液並の成分配合が魅力。
ローズを彷彿とさせるクリアなピンクのジェルとローズの贅沢な香りが、上質なハンドケアタイムを演出します。
ジェルなので、こってりしすぎることもなく、春や夏など、比較的暑い季節でも使いやすい使用感となっています。
ナールス ロゼは、35gで2,640円(税込)。
3本まとめて購入をすると、7,920円(税込)のところが6,600円(税込)に!
1,320円お得なだけでなく、ラッピング袋3枚付き、さらに送料も無料になります。
贅沢なバラの香りに包まれながらハンドケアしたい方はもちろん、プレゼントとしてもおすすめ。
春は出会いと別れのシーズンです。
今までお世話になった方たちへ、ナールス ロゼをプレゼントするのはいかがでしょうか?
*カルボキシメチルフェニルアミノカルボキシプロピルホスホン酸メチル
<参考記事>
*絶世の美女愛用!バラの女王ダマスクローズの5つの効果で憧れの美肌
8.まとめ
ビューティーアロマ認定講師の北口慈子さんに、脳(心)と肌悩みの関係や香りによる肌悩みの解消のポイントをご紹介いただきました。
また、自律神経が乱れたときの香りの活用法からおすすめの香りの種類までご紹介いただきました。
いかがだったでしょうか。
春は季節的な影響だけでなく、環境の変化によりストレスをためやすい時期。
心の状態や肌の状態に合わせて、適切な香りを用いると香りは肌悩み解消の味方になってくれます。
もちろん、香りは日々の生活を彩るエッセンスのようなもの。
規則正しい生活リズム・適切な睡眠時間・栄養バランスの整った食事・正しいスキンケアを心がけるとともに、香りを上手に生活に取り入れて美肌を目指しましょう。
この記事「春の変化によるストレスと肌悩みは香りで癒されて対策を」が、ナールスエイジングケアアカデミーの読者の皆様のお役に立てば幸いです。
著者・編集者・校正者情報
(1章及びまとめの執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)
京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務。その後、医学出版社、医学系広告代理店勤務を経て、現職に至る。
医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。
一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト。
著作
メディカル視点で「カッコイイ」を目指す。大人のスキンケア&美容ブック
(共著)
(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)
大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。
ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。
当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。
そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報をご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。
ぜひ、ご登録をお待ちしております。
▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから
nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」
SNS Share
\ この記事をシェアする /